カーボンニュートラルは、日本語で「炭素中立」とも呼ばれる概念です。「脱炭素」と意味合いが似ており、その具体的手法として示されることがあります。
生産活動においては、排出する二酸化炭素量と削減する二酸化炭素量を同じ値(ニュートラル)にすることをいいます。また、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする取り組みなど、技術開発や経済活動としても捉えられています。
カーボンニュートラルの必要性

エネルギーの存在は人々が社会生活を営むうえでの基本的な土台となっています。その中で、現在使用されている多くのエネルギー(石油・石炭・天然ガスなど)は「炭素」を含む化石燃料を燃料源としています。炭素は酸素と結合して二酸化炭素となり、大気中に放出されます。
二酸化炭素は温室効果ガスと呼ばれる地球の表面温度を上昇させる気体の構成要因です。二酸化炭素の排出量が増え続けると地球温暖化に歯止めが利かなくなります。これにより、様々な気候変動を引き起こすと予測されています。
現状においても、大型台風の頻発化、暖冬、海面温度の上昇といった異常気象が多々見られるようになっており、地球温暖化の片鱗が感じられます。こうした状況の中、持続可能な社会を実現するための取り組みとして”カーボンニュートラル”が生まれました。
カーボンニュートラルの仕組み

二酸化炭素排出の埋め合わせ
カーボンニュートラルは地球温暖化を抑えるために必要な取り組みです。しかし、その一方で人々が生活を営んでいくうえで二酸化炭素の排出量をゼロにすることが困難な分野も多々あります。削減が難しい事象においては、その排出分を埋め合わせるために”吸収”および”除去”といった手続きを行います。
吸収
植物は光合成により二酸化炭素を吸収し酸素を放出する活動を行います。この特性を活用したものが「吸収」です。つまり、植林行動により排出量の埋め合わせを行うことをいいます。しかし、植物を育成する土地や知識を持たない企業が植林を行うのは困難です。そこで、植林に直接携わっていない事業者に関しては、森林所有者等が創出する「J-クレジット」を購入する仕組みがあります。
除去
CCSと呼ばれる技術を用いて地中へ二酸化炭素を貯留することを「除去」といいます。CCSは、大規模な設備を所有する事業体により実施されます。そのため、個々の事業者が行う活動とは見なされていません。国全体としてカーボンニュートラルの実現に寄与する仕組みです。
カーボンニュートラルをめぐる動き

石油依存からの脱却
近年では植物由来の燃料を用いるなど石油依存を脱却する取り組みが加速しています。例えば、バイオマスエタノールの活用やバイオプラスチックの開発といった新たな手法が注目を集めています。また、再生可能エネルギーによる発電も活性化しています。再生可能エネルギーは、太陽光、水力、風力など自然の力をもとにして電力を創り出します。こうした分野の比率が向上していくと、石油だけでなく多様な発電方法を選択していくことができます。
支援と補助
支援の例として、経済産業省が発表した「グリーン成長戦略」があります。これには、カーボンニュートラルに向けた投資、研究開発への補助、事業再編、税制優遇の改革が記載されています。カーボンニュートラルの取り組みに対して各種の優遇措置を採る手法です。民間からの一層の投資喚起や需要の活性化を後押しする狙いがあります。
自動車産業
自動車業界では、かねてからCO2の排出を削減するエコロジー化が進められていました。昨今においては、これに加えて製造時の二酸化炭素削減にも力を入れています。自動車はCO2の排出と切っても切れない関係性がありました。環境性の問題に対し責任が重大であり、また取り組みのスピードも速い業界です。近年では、電気自動車の開発など環境面に優れた取り組みが主流となりつつあります。
投資行動
欧米を中心として「ESG投資」といった環境への資金注入が活性化しています。環境性に優れた企業や製品に対して投資を行う指標のようなものです。
日本においても要項に環境性を盛り込んだ投資活動が徐々に増加しています。今後の発展が期待されている投資分野のひとつです。
カーボンニュートラルの課題点

化石燃料依存からの脱却
現在の社会活動を営むうえで製造や輸送において化石燃料を使用しないことは困難です。化石燃料によって排出される二酸化炭素をゼロにすることは現実的ではありません。そのため、製品ライフサイクル全体を通してカーボンニュートラルの実現を試みる必要があります。エネルギー調達の部分から化石燃料への依存を取り除いていくことが重要です。
削減のジレンマ
カーボンニュートラルの取り組みを拡大し植物由来の燃料や原材料への変換を進める。これを実現しようとすると、植物を育成するための広大な土地が必要となります。例えば、日本では国土面積の約7倍の土地が必要だと試算されています。現状でこれらを達成することは非常に困難です。
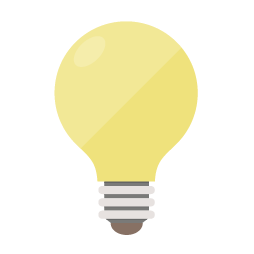
気候変動は世界全体の課題となっています。その中で、カーボンニュートラルは自治体や企業だけに任せることはでません。個人でも考慮していくべき事象です。しかし、現実的にまだまだ大きな障壁が残されている分野でもあります。今後、次世代へ環境資源を残し持続可能な社会を作りあげるために努力を重ねていく必要があります。





コメント